どうも気になるので「玄米せんせいの弁当箱」、読みなおしました。
それによると、お雑煮の文化圏的わけかたで、玄米せんせいは
・角餅すまし汁文化圏
・丸餅赤味噌文化圏
・丸餅白味噌文化圏
・小豆汁文化圏文化圏
・丸餅すまし汁文化圏
と、5つに分けております。
ネットで検索してみるに、架空の先生ではなく、実在する神戸山手大学教授の奥村彪生先生はまた別な分類法をとってあります。
・すまし文化圏
・赤味噌仕立文化圏
・白味噌文化圏
・小豆汁文化圏
・角餅文化圏
・丸餅文化圏
6つに分類してます。
以下が奥村彪生先生作成の分布図です。
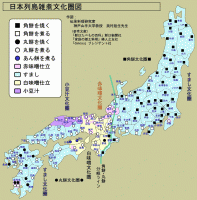
これを見る限りでは味噌仕立てで角餅を使用するところは見当たらず、基本的に玄米せんせいと同じですね。あとはその餅を煮るか焼くかの違いを分布図に落とし込んでるだけです。
携帯の方は見づらいでしょうから書きますが、奥村先生の作られた分布図で、真ん中あたりに縦、つまり南北に伸びる線を境に角餅文化と丸餅文化に分かれております。境界線より西は丸餅、東は角餅です。
で、高知は西方に「足摺」と書かれてその下に丸印が、つまり丸餅文化圏ということになってます。でも、別の資料によりますと、高知の場合、足摺の方は丸餅ですが高知は角餅となってます。中村へんには一条さんの、高知には東方から来た山内家の影響があるのかもしれません。北陸酒田もその地方では唯一丸餅文化ですが、これは京都からの廻船で丸餅を運んだのではないのかなぁ・・・
と思ってたら、サイトにちゃんと書いてました(笑)
以下です。
●丸餅・・・古風。京都の文化を受けた土地。
●角餅・・・江戸生まれの新風。江戸の文化を受けた土地。
●味噌仕立て・・古風。京都の文化を受けた土地。江戸の文化を一切受け入れなかった土地。
●すまし仕立・・・西日本ですまし仕立の地域は、参勤交代で江戸の文化を取り入れ、古風の丸餅と融合させた。鹿児島では角餅を用いる家が多い。
こう見てくると、餅の文化ひとつとっても当時の商いや、権力者の動向が伺えて楽しいですね。
で、なぜ角とダルマやなかった丸餅があるのかといいますと、本来、魂を表す丸型だった餅ですが、作り方が簡単で保存に便利な角餅が作られるようになり、江戸や寒冷地で使われるようになったからだとか。比較的暖かい西日本で、いまだに丸餅が多いのは、古来からの伝統を崩す必要もなかった、ということですね。それと、スーパーなんかで取り扱ってる餅に角餅が多いのは、メーカーが関東に片寄ってるというだけではなく、やはり作り方と保存の問題もあったのですね。
それにしても、丸いお餅は魂だったなんて、食べるのが怖い 。
。
それによると、お雑煮の文化圏的わけかたで、玄米せんせいは
・角餅すまし汁文化圏
・丸餅赤味噌文化圏
・丸餅白味噌文化圏
・小豆汁文化圏文化圏
・丸餅すまし汁文化圏
と、5つに分けております。
ネットで検索してみるに、架空の先生ではなく、実在する神戸山手大学教授の奥村彪生先生はまた別な分類法をとってあります。
・すまし文化圏
・赤味噌仕立文化圏
・白味噌文化圏
・小豆汁文化圏
・角餅文化圏
・丸餅文化圏
6つに分類してます。
以下が奥村彪生先生作成の分布図です。
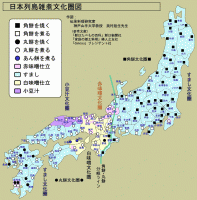
これを見る限りでは味噌仕立てで角餅を使用するところは見当たらず、基本的に玄米せんせいと同じですね。あとはその餅を煮るか焼くかの違いを分布図に落とし込んでるだけです。
携帯の方は見づらいでしょうから書きますが、奥村先生の作られた分布図で、真ん中あたりに縦、つまり南北に伸びる線を境に角餅文化と丸餅文化に分かれております。境界線より西は丸餅、東は角餅です。
で、高知は西方に「足摺」と書かれてその下に丸印が、つまり丸餅文化圏ということになってます。でも、別の資料によりますと、高知の場合、足摺の方は丸餅ですが高知は角餅となってます。中村へんには一条さんの、高知には東方から来た山内家の影響があるのかもしれません。北陸酒田もその地方では唯一丸餅文化ですが、これは京都からの廻船で丸餅を運んだのではないのかなぁ・・・
と思ってたら、サイトにちゃんと書いてました(笑)
以下です。
●丸餅・・・古風。京都の文化を受けた土地。
●角餅・・・江戸生まれの新風。江戸の文化を受けた土地。
●味噌仕立て・・古風。京都の文化を受けた土地。江戸の文化を一切受け入れなかった土地。
●すまし仕立・・・西日本ですまし仕立の地域は、参勤交代で江戸の文化を取り入れ、古風の丸餅と融合させた。鹿児島では角餅を用いる家が多い。
こう見てくると、餅の文化ひとつとっても当時の商いや、権力者の動向が伺えて楽しいですね。
で、なぜ角とダルマやなかった丸餅があるのかといいますと、本来、魂を表す丸型だった餅ですが、作り方が簡単で保存に便利な角餅が作られるようになり、江戸や寒冷地で使われるようになったからだとか。比較的暖かい西日本で、いまだに丸餅が多いのは、古来からの伝統を崩す必要もなかった、ということですね。それと、スーパーなんかで取り扱ってる餅に角餅が多いのは、メーカーが関東に片寄ってるというだけではなく、やはり作り方と保存の問題もあったのですね。
それにしても、丸いお餅は魂だったなんて、食べるのが怖い
 。
。
| ホーム |

